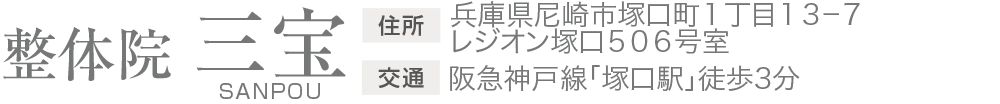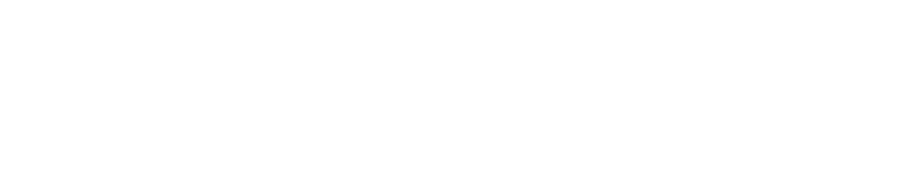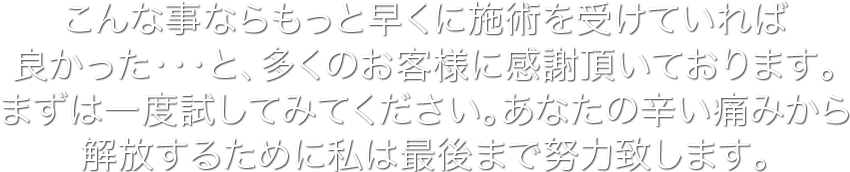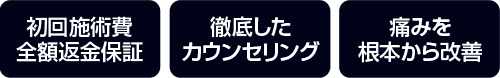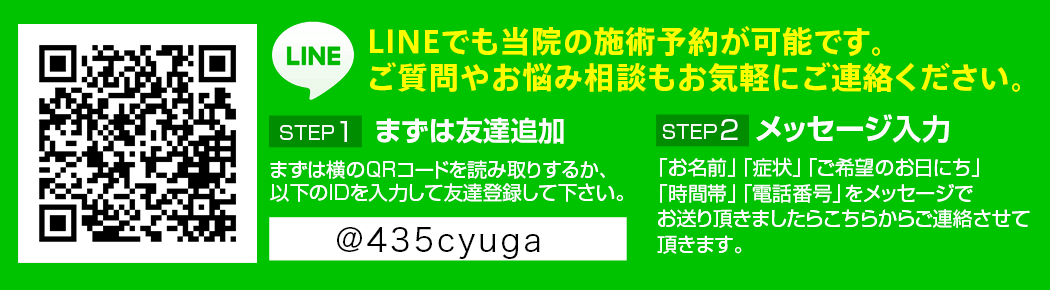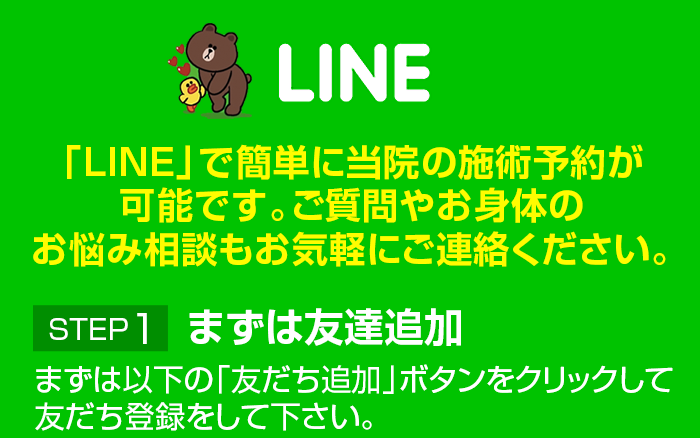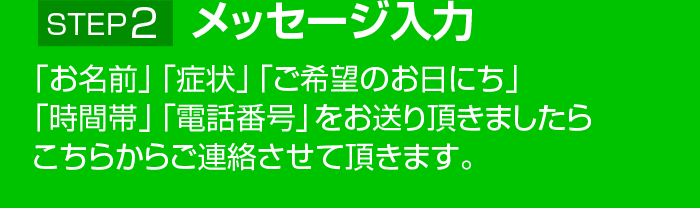2023/08/18(金)
”暑くない”は危険なサイン?!
カテゴリー:院長ブログ
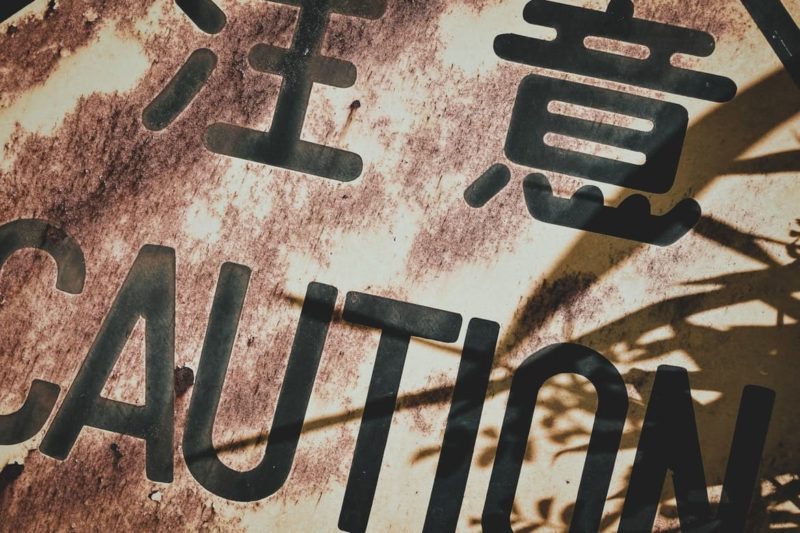
今回のテーマは「”暑くない”は危険なサイン?!」についてです。
以前、熱中症対策!自分は大丈夫は危険!!において、熱中症について解説しました。
熱中症は対策をしっかりと行なえば、確実に防げる病気です。
ただ、人間は加齢と共に自分の体の異常に気付きにくくなってきます。
お年寄りについて、こんな話を聞いたことはありませんか?
「家は全然暑くないから、クーラーは使っていない!」
「汗もかかないし、トイレに頻繁に行くのが嫌だから家では水分は殆ど摂っていない!」
こういった話は、直接だったりニュース等で間接的であったりで聞いたことは1度はあると思います。
消防庁の2018年のデータによると、56.5%の方が自宅で熱中症に罹り死亡に至ったというデータがでています。
ではなぜ、暑い状況下で暑くないと感じたり、喉が乾かないのか?この理由を簡単に解説していきます。
暑さを感じない・喉が乾かない状態になってしまうのか?の原因を一言で言うと、
「加齢」
これが結論です。
人間の体は、暑ければ熱を体に溜め込まないように体外に放出して体温を下げようとしますし、寒ければ熱を外に逃がさないように体内に溜め込もうとします。このような体温調節を必ず行っていま。
体温調節の方法は主に2つあります。
➀行動性体温調節
②自律性体温調節
➀行動性体温調節とは、寒ければ上着を着たりと厚着をしますし、暑ければ薄着になったりエアコンをつけたりします。これは、自らの意思で体温調節をしようと試みます。
②自律性体温調節とは、無意識下で体温調節をしようとする反応です。
例えば、寒い時に体が震えることによって熱を生産させようとしたり、暑い時は汗をかいて熱を下げようと試みます。
この体温調節に重要な2つの内、
➀の自律性体温調節機能が加齢と共に低下してしまうことで、暑さを感じにくくなくなったり、喉が渇きにくくなるのです。
自律性体温調節機能の低下により、
・汗をかく機能が低下する
・血流調整機能が低下する
・皮膚の温度センサーが低下する
汗をかく機能が低下するので熱が体に蓄熱されて高体温状態になったり、
血流調整機能が低下するので熱が体に蓄熱された場合、血流を増やして熱を外に放出することができなくなったり、
皮膚の温度センサーが低下するので暑いのを暑いと感じにくくなってしまいます。
こういうった体の機能低下は、例外なく皆さんに起こります。
特にこういった機能低下が顕著なのが、65歳以上だというデータがでています。
ただし、あくまでも平均値なので個人差が非常に多いと考えてください。
20~30代で機能低下が起こる場合もありますし、70代になってから機能低下が顕著になる場合もあります。
20~30代の場合は自律神経の乱れなどで、一過性で起こるケースが多いです。
・汗をかく機能が低下する
・血流調整機能が低下する
・皮膚の温度センサーが低下する
こういった機能低下は自身で気づくのは意外と難しい部分があります。
ですから、家族がいかに変化に早期に気づいてあげるか?ここが重要になってきます。
自身でできることとしては運動を習慣化させて、汗をかいたり、血流増加を強制的に促すようにしたり、
体温計や湿度計を設置して、数値と自分の感覚にズレがないか?を普段からチェックすることをお勧めします。
こういった対策をする事で、熱中症は勿論ですが様々な不調を防ぐことができます。
原因が何なのか?それをしっかりと理解していれば、しっかりとした対策が打てます。
ぜひ、あなた自身や家族の状態をチェックしてみてください!
それでは、本日はこの辺りで失礼します。
何かご質問などございましたら、LINE・メールでお問い合わせ下さい。
また、こんなことについて書いて欲しい!というテーマがあれば是非ご連絡ください。
過去の記事はこちら